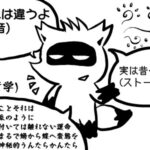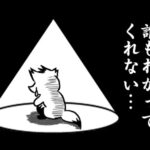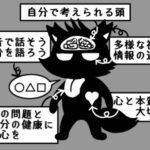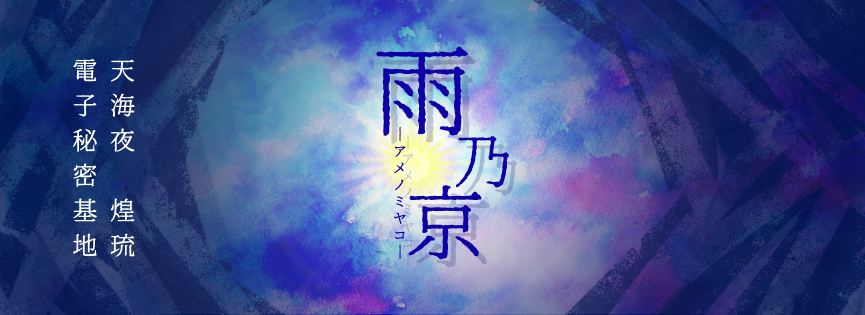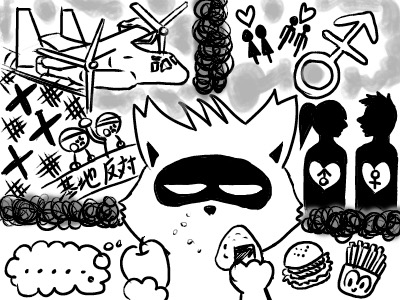
陰と陽を和合・浄化するジェンダレス妖怪
天海夜 煌琉(あまみや こうりゅう)でございます。
魑魅魍魎(ちみもうりょう)の情報社会で様々な情報があふれる中、
世間で言われるところの「陰謀論」や「都市伝説」に触れる機会も多くなってきた。
そんな中で、「なぜ僕が『世界の闇』を調べるようになったのか」
というテーマで執筆をし始めることにした。
これは、ただむやみやたらに情報に飛びつくことをしないためにも、
「なぜ自分はこのような情報を調べて、人に広めたいと思ったのだろう?」
と、自分自身の根本的な部分や基本な考え方に帰ってみる試みだ。
今回は、
2012〜2019年にかけてどのような情報を得ていたのか
別の視点での情報を得たことで変化した自分自身の価値観
などを主に話していきたい。
そもそも僕が情報を自分で調べるようになったきっかけ…
つまり、自分の価値観に大きなパラダイムシフトが起こった出来事というのは、
大きく分けて2つある。
①東日本大震災
②2020年からのウイルス騒動
である。
なお、東日本大震災は2011年でウイルス騒動は2020年ということで、
2012年〜2019年までの7年間は何を考えていたのか?
今回はその期間に調べた内容を、
①食の闇
②沖縄の政治・基地問題
③LGBTQ
という3つのテーマに分けて振り返っていきたい。
前回↓
①食(添加物や農薬など)の闇
東日本大震災と原発事故、そしてベジタリアンとの出会いをきっかけに
SNSなどを使って自分でも情報を取ることが当たり前になっていった。
特に健康の分野や、「食の闇」に関しては興味関心が高かった。
いろいろ調べていくうちに、
特に日本は使用されている農薬や食品添加物の種類が多く、
さらにその表示がゆるい国とされているとわかった。
それからというもの、加工品はできるだけ避けて、
できるだけ無添加の商品を選ぶようになった。
なぜ僕が食に注意するかというと、
もし自分が「病気」になってしまったら、仕事や活動ができなくなり、
自分自身の生活ができなくなる。
その不安から、日本に生きている以上、完璧ではなくて良いけど、
「病気になるリスクはできるだけ避けよう」と考えるようになったのだ。
自分が病気にならないことで、治療費を浮かすこともできるしね。
そして、同じ金額を使うのであれば、病気ではなく、
自然免疫を高めることに自己投資をしたいと思い、
今ではこの考え方が当たり前になっている。
特に日本は添加物や農薬、水道などの闇が深い。
そのため、自然食品店で買い物をすることも増えたし、
有機野菜を買うこともあるし、
使っている調味料に関しても、オーガニックかつシンプルな素材で、
なおかつ伝統的な製法で作られているものを選ぶようになった。
また、ベジタリアンの考え方に触れて、ヴィーガンとはいわなくても、
ゆるベジのスタイルで、お付き合いで肉食をすることはあっても、
自宅では動物製品をほぼ断っていた時期もあった。
ただ、野菜に関しては普通にスーパーやJ◯で買うことも多かったし、
マ◯ドナルドは嫌いだからほとんど行かないのだけれど、
牛丼屋などの安いファストフード店などはよく利用していた。
毒だからといってなんでもかんでも制限するのは、
かえってストレスになると思ったからだ。
ただし、J◯の闇を知ってからは、J◯も今ではほとんど利用していないし、
牛丼屋も今はごくごく稀にしか利用しない。
相変わらずマ◯クは一年に一回行くか行かないかの頻度。
「買い物は選挙」とよく言うし、
自分と価値観が近いオーガニックのお店で食事をしたほうが、気持ち良くお金を払えるし、
普段の自炊でも、有機野菜や自然栽培の野菜をメインに選ぶようにはなった。
②沖縄県内の問題〜政治や基地問題など〜
食を含め国内のあらゆる問題も深刻ではあるが、
沖縄は沖縄で、基地問題や中国の問題などもあるし、
「県内のメディアは偏向報道が酷いな」
と思うようにはなっていった。
僕も沖縄県在住者を対象とした、
保守寄りのFacebookコミュニティに入っていたことがあって、
そこから政治や基地問題に関する情報を得ていた。
そのあたりから、メインのメディアが報道しない他の視点で、
一つの事実を観察するようになった。
僕はそれまで自身がトランスジェンダーということもあり、
LGBTQの人々と関わることも多く、左寄りの活動家である知人も多かった。
しかし、個人事業主として独立したいという思いがあったからか、
ビジネス関係の人と関わることも多くなり、
2015年前後くらいから少々右寄りの考えにはなっていった。
そして、色々調べていくうちに、
特に基地問題に関しては、印象操作が酷いと感じるようになり、
今まで左寄りの知人から得ていた情報も疑うようになっていった。
たとえば…基地問題で運動をしている人たちは、
ほとんど沖縄県民じゃないなどである。
確かに沖縄の人はのんびりしていて平和主義者なので、
激しい活動をしたり早起きをしたりなどの面倒なことはしたがらない県民性だ。
活動家のほとんどはプロ市民と呼ばれる人で、やることが悪質な印象を受ける。
活動家の仕業か知らないが、基地のフェンスにバッテンのマークが貼られているのを僕も見たけど、
正直あまり良い気分ではない。
米軍のFacebookページでも、
軍の人が地元の子どもたちと仲良く交流している写真も見られるし、
ビーチクリーンをしている人達もいる。
経済的にも、基地の恩恵を受けている地元の人たちがいるのも事実だ。
あと、辺野古と言うと環境問題がよく話に持ち出されるけれど、
辺野古はジュゴンの餌場であるにすぎず、住処なわけではないみたいなんだよね。
そのため、こういったニュースは、
自分たちにとって都合よくコントロールするために、
環境問題や動物の話を持ち出すことで、受け取る人の感情を操作しているとも言える。
以上のような事実や報道の目的を知ることで、
特に「一方的な視点での印象操作」や
「実は全く因果関係のない問題で煽ってくる報道」などには
得に注意するようになった。
実際このような「人に罪悪感を抱かせるような心理作戦」って
詐欺師の常套手段だから、騙されないように注意。
沖縄の実態についてわかりやすい動画↓
③当事者だからこそ懸念しているLGBTQの闇
ただ、一方で、保守派の人は男女平等などのジェンダー問題に批判的な人も多く、
大きなショックを受けたことがあった。
とあるLGBTQのイベントに対する県内メディアの報道の仕方に関して、
批判的なコメントが寄せられていたのだ。
「イベントの来場者はどう考えても数を盛っている」
「気持ち悪い」
「性の多様性じゃなくて性の異様性」
などといった書き込みだ。
まぁ今思えば、確かにイベントの来場者の数字はかなり盛られていたと思う。笑
それ以外の言葉はあまり好ましくない表現だが…。
LGBTQのニュースに対するこの反応を見て、
右寄りの人々は性別不明者を嫌う傾向にあるのはわかったが、
当事者としてちょっと言葉が酷すぎると思い、そのコミュニティは退会した。
しかし、今では彼らのような気持ちになるのはすごくわかる。
僕も当事者でありながら、
マイノリティがマジョリティの意見を抑えて、優勢になってしまう流れは大変危険だと思っている。
ホルモンも性別適合手術もしていない、明らかに男性の人が
「性自認は女性だから」と言って女性更衣室に入ることに、女性が「嫌」と言えない。
そういう「正常な反応」を批判する空気が、社会全体として作られてしまうのは良くない。
そもそもの話、人は平等なのが当たり前だし、
特に日本は元々性に対して寛容な国なのだから、
LGBTQが受け入れられるように見えるのは、「ただ元に戻っただけ」のことである。
恐らく、LGBTQ嫌いの人の中には、こういった背景や裏の意図も考えて、
「LGBTQの裏で蠢いている勢力」に対して嫌悪感を抱いている人もいると思われる。
僕も今では、「LGBTQは利用されている」と確信しているし、
「虹」もすっかりSD◯sのイメージが付いてしまったし、
そもそも自然現象の「虹」に対しても、
「人や民族によっては必ずしも良いイメージとは限らない」
とも思うようになった。
そういった経緯もあり、
既存の言葉で自分のアイデンティティを決められるのは
個人的にあまり好きではなくなったし、
自らをLGBTQと言うこともほぼ無くなった。
また、以前はトランスやゲイタレントが活躍していると嬉しく思ったけど、
今は全くそう思わない。
確かに共通点があるのは嬉しいことであるが、
「LGBTQだから」応援したいわけではない。
結婚できなくても同性が好きでも性別が不一致でも
「自分」は「自分」。
「あなた」は「あなた」。
「こういうタイプの人たち」といった括りで、誰かによって認められるんじゃなくて、
自分が自分自身を認めることが大切だ。
…と、今では強く思うのだ。
まとめ:どの分野も闇が深いけど、その分目が覚めた
今回は2012年〜2019年の間、新しい視点で得た情報として、
①食料の闇と健康に対する考え
②沖縄の基地問題と実態
③LGBTQの闇
を主に説明してきた。
僕自身、だいぶ世間の常識やテレビなどの情報に毒されてきたんだなって自覚したわ。
その分ショックだったけれど、それがあったから今の自分があるんだなって
自分のことがちょっと好きになったよ。
この他にも、学校で教えられた歴史が実は間違っていて、
それらが一方の視点で語られているだけの自虐史観であることも学んでいたが、
このテーマに関しては今回は割愛した。
歴史に関しては、また別の機会に語っていきたいね。
さて、次回はいよいよ、
例のウイルス騒動に対する考え方の経緯を書いていこうと思うので、お楽しみに。
次回へ続く。