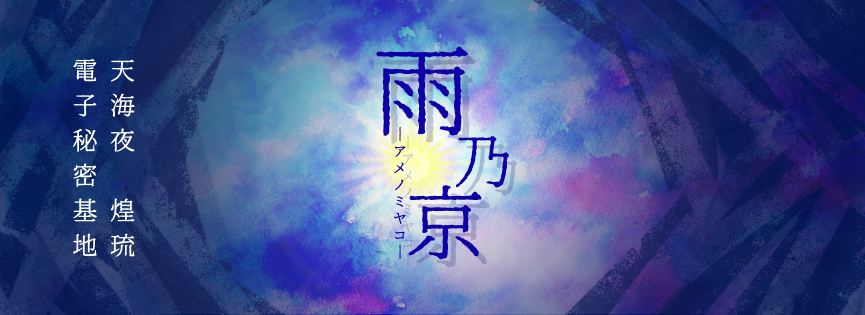天海夜 煌琉(あまみや こうりゅう)でございます。
前回は鹿児島・知覧の旅の前半ということで
知覧特攻平和会館へ訪れたときのことを書いた。
今回は後半ということで
武家屋敷庭園のことについて書いていきたい。
前回↓
知覧特攻平和会館から武家屋敷庭園へ向かうには
バスを利用した。
その際、降りるバス停に関して
親切なバスの運転手さんから良いことを教えていただいた。
「武家屋敷に行くなら、”中郡”というバス停で降りるのが良いですよ」
とのことだった。
そのほうが歩くのに便利だという。
確かに、地図で見たところ、
中郡からだと折り返す必要もなく、 一直線でスムーズに庭園を周れそうだ。
というわけで、運転手さんの言う通り、
中郡で降りる。


自然が豊富で心地よい。
武家屋敷に入る前に入場料を支払うのだが、
こじんまりしたお店でおばあさんが一人で運営されていた。
入場料の500円を払ってレッツゴー。
(2020年現在は530円らしいです)


これから先だが、
庭園は一般公開されてはいる一方で、
地域の方の生活の場でもあるとのこと。
なので、印象的だったものだけ文字とイラストで紹介したい。

まず、武家屋敷庭園は、「薩摩の小京都」とも言われ、
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されているそうな。
さらに、そのうち7つの庭園が国の名勝となっているようだ。
その7つの庭園のうち、1つは「池泉式」、
他はすべて「枯山水式」の庭園だそうだ。
まず、池泉式とは何かと言うと…
大きな池を中心に配し、その周囲に園路を巡らして、築山、池中に設けた小島、橋、名石などで各地の景勝などを再現した。園路の所々には、散策中の休憩所として、また、庭園を眺望する展望所として、茶亭、東屋なども設けられた。
対して、枯山水式とは、以下の通りである。
枯山水は水のない庭のことで、池や遣水などの水を用いずに石や砂などにより山水の風景を表現する庭園様式。例えば白砂や小石を敷いて水面に見立てることが多く、橋が架かっていればその下は水である。石の表面の模様で水の流れを表現することもある。
なるほどね〜。
僕自身、このような知識があった上で巡ったわけではなかった。
しかし、そう言われてみると確かに、池がある庭園はごく一部で、
他は全て砂や岩で構成された庭園だった。
京都の庭園もそうだが、
何かを岩や砂、草木、水で表現した日本の庭園は
美しい芸術品である。
なので、僕は日本の庭園を歩くのがとても好きなんだ。
しかし、こちらの武家屋敷は、
石敢當やヒンプンなど、琉球の影響も強く受けているともわかった。
南九州市である知覧は沖縄にも近いこともあるし、
美しさを愛でる気持ちだけじゃなくて、
親近感も覚えたのだった。

そう言えば、庭園を巡っていると、
気になるものを見つけた。
それはとある庭園にある屋敷にて、
「男玄関」と「女玄関」というものを
見つけた時である。

男女どちらでもない僕は
「どっちへ入ったらよいんだろう…?」
と迷ってしまったわけだが…
調べてみたところ、これは男女差別というより、
これは身分や役割を分けるという意味があったらしい。
相反する意味や表現として「陰と陽」などがあるが、
それを男女で表したということなのかな?
しかも、中は立入禁止だったものだから
結果的に、どちらからでも上がれなかった。
その代り、外から室内の様子を見ることはできるけどね。
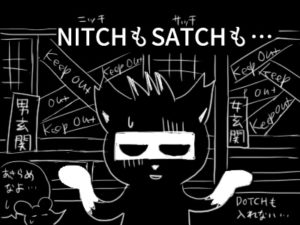
※実際にはこのような「Keep Out」のバリケードは無いよ。
というわけで、男か女か悩む時間も不要だったわけだ。
「男」とか「女」とか、ついつい反応しちゃう。
それは自分だからじゃなくて、
多くの人に共通している性(サガ)なのであろう。

…とまぁ、こんな感じで雨がそこそこ激しい中、
武家屋敷庭園を巡ったのだった。
鹿児島中央まで戻った後は
お待ちかねの晩ごはん。

カツ丼を食べた。
こちらは卵とじじゃないカツ丼で
かつキャベツがたっぷり敷かれているのが特徴的。
ボリュームたっぷりな黒豚を
リーズナブルにいただけたので大満足!!
なのであった。
さて、明日はいよいよ鹿児島編・最終日。
明日はいよいよあの島へ向かう?
次回へ続く!!↓